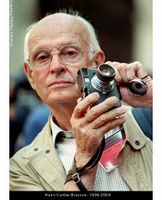Uccello - La Bataille de San Romano (ウッチェロ - サン・ロマーノの戦い)
Collection du Musée de Louvre (ルーブル美術館コレクション)
幅広い階段を小走りに駆け上がり、人々の間をすり抜けながら、広大なルーブルの連なる展示室を通り抜けていく。矢印と共にあちこちに現れる、主役の貫禄たっぷりのジョコンダ婦人(モナ・リザ)の微笑を横目に見ながら、イタリア・ルネサンス絵画の部屋の入り口に辿り着くと、ジョットの聖母子像が気品に満ちた静かな迫力で迎えてくれる。ここでほっと息を整え、さらに歩みを進めると、すぐにその絵が見えてくる。ウッチェロのサン・ロマーノの戦い3部作のひとつ、『La Contre-Attaque de Micheletto da Cotignola (ミケレット・ダ・コティニョーラの援軍)』[1435-40?] だ。

縦1メートル81センチ、横3メートル16センチのこの作品は、3メートル離れて立って、ちょうど視野に全体像が収まるくらい。暗い背景に何本もまっすぐに伸びる槍のシャープなライン、そして中央に集まる人や馬のかたまりに感じられる、外に弾けていこうとするようなエネルギーの凝縮。ラインや構図が生み出す緊迫感と、押さえた暗い色と描かれた一群のボリュームがもたらす、どっしりとした存在感。前に立つと、その絵に満ちるエネルギーに圧倒される。
1432年、ライバル都市、フィレンツェとシエナの間に起こり、フィレンツェの勝利に終わったサン・ロマーノの戦いを描いたこの3部作は、フィレンツェのメディチ家に3枚そろって飾られていたが、今はパリのルーブル、ロンドンのナショナル・ギャラリー(『フィレンツェ軍を指揮するニッコロ・ダ・トレンティーノ』)[下図左]、フィレンツェのウフィッツィ(『ベルナルディーノ・デラ・チャドラの落馬』)[下図右]に所蔵されている。それぞれ別々になら見たことがあるが、 いつかウッチェロ大回顧展などといって、3作一堂に揃って展示されることがあれば、世界のどこにいたとしても見に行きたい。


15世紀のイタリア・ルネッサンス、視覚的リアリズムを追求するこの時代の初期に活躍したウッチェロは、当時最新のテクニックだった遠近法に取り付かれていた画家として知られている。サン・ロマーノの戦いシリーズの中でも、そこかしこに遠近短縮法を使っている。ロンドンの例を見てみよう。前傾で倒れている兵士(下、拡大図)、地面に散らばる槍や武具。ルーブルの絵においても、あらゆる角度から描かれる馬の体に、ウッチェロの遠近法熱が見て取れる。

立体感と奥行きの表現にこだわるあまり、静止した彫刻を写したような硬さがあるのは否めない。時代的にもう少し後に出てくる、かの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチのように、光と影の効果、または空気の表現によって硬い輪郭を和らげ、より自然に遠近感を出すことを、ウッチェロはまだ知らなかったと、ゴンブリッチ先生は指摘する。 (E. H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon, 1995, p.256)
しかし、ウッチェロのすごさはその技法的ぎこちなさを超え、それすらも魅力のひとつに感じさせてしまうところにある。ウッチェロの幾何学的構成に対する関心は、緊張感のある画面構成を作り出している。暗い色調で描かれた馬の重なり、兵士たちの集合のかたまりの重さに対して、まっすぐでシャープに伸びる槍のラインの明るさ、軽やかさ。このラインの生むリズムや配色、特に朱色に近い、この時代独特の赤を効果的に使うことによって、画面に動きが出てくる。確かに、ひとつひとつのモチーフは木彫りの彫刻のようであっても、全体の構図や効果的な色使いによって生まれるリズムが、画面にダイナミックな動きとエネルギーを生み出しているのである。
また、画面上部の槍の線、そして画面下部の馬や兵士の足の線が、中心のかたまりから外側に向かって放射線状に、リズミカルに広がっている。この線が、今にも外に向かって飛び出していきそうなこの集団の士気溢れるエネルギーを感じさせると同時に、逆に見る者の目を自然に線の集まる中心、主役となる人物へと導く働きもしている。この大画面に、これだけの情報を詰め込みながら、存在感と緊張感を持ってダイナミックに主題(この戦いの英雄)をみせる、見事なコンポジション(画面構成)は、さすがウッチェロだ。新しい芸術の時代の幕開けの高揚感、挑戦心、そして喜びに満ちたウッチェロ芸術は、今の時代の目にも刺激的で新鮮さを失わない。


そのウッチェロの彫刻的な雰囲気がますます魅力的な小作品が、ロンドンとパリにある。『竜と戦う聖ゲオルギウス(Saint George and the Dragon / Saint Georges terrassant le Dragon)』という同じテーマで描かれた2点で、ひとつは前述のロンドン・ナショナル・ギャラリー[上図左]、もう1点はパリのジャックマール・アンドレ美術館(Musée Jacquemart-André)[上図右]にある。
ナショナル・ギャラリーのほうが、斜め前の角度から竜と騎士を描いていて少し複雑化しているが、ジャックマール・アンドレのほうは、みんな横向きで構図も単純、竜も着ぐるみのような愛らしさがある。青、白、赤、緑のシンプルでクリアな色使いで、おもちゃ箱から人形を取り出して並べたみたいなコンパクトなまとまり、かわいらしさだ。ジャックマール・アンドレの屋敷の小さな一室に、木製の家具などと共に飾られているのがとても合っている。このポップさとシックな落ち着きの、なんともいえないバランスもまた、ウッチェロの魅力のひとつだ。