Andy Warhol in the Pre-Pop 1950s (プリ・ポップ時代のアンディ・ウォーホル)
西荻窪に、たまに行けば毎回2時間くらい居座る“音羽館(おとわかん)”という古本屋がある。いつも何かしら映画や音楽やアートなどの面白い本・雑誌・画集などが見つかり、良心的な値段で品揃えがいいからか本の回転もなかなかいい。ものすごく専門的にこだわっている、というのではないが、逆に気軽に構えず行くことができるのがよい。店も明るくきれいで居心地いいので、特に探している本があるわけではなくてもついフラフラっと行く。行くと何かしら買いたくなるのでたまにしか行かないのだが、しばらくすると「そろそろ行かないとな」という気になる。今回も前回から1ヵ月半くらい経っていたので、貧乏を引きずりながらもちょっとウキウキした気分で店のドアを開けた。
見る順番はだいたい毎回決まっている。文庫、新書からざっと見て、絵本をちらちら覗いて、デザインや音楽の雑誌類のタイトルに一通り目を通して、思想書の前をたらたら通り過ぎ、セレクトして置いてある新刊のタイトルを眺める。それから写真関係に移って、気持ちが集中してきたところで映画の棚に向かい、そのあたりを行ったり来たりしながら、最後にアートのコーナーに進む。
買い始めるときりがない。お金もない。だから次から次に本を持ち代えて、最終的に手の中に残った一冊を買う。この日は何度もいろんなページを開いて吟味した、ユリイカの1989年のバックナンバー『ヌーベル・バーグ・30年』に決まるか、というところだった。その最後の最後に目に入ってきたのが、このウォーホルのイラストレーション・ブックだった。「今日ここで求めていたのはこんな出会いよ」という胸の高鳴りに、ユリイカはあっさり負けた。
"Drawings and Illustrations of the 1950s"
『アンディ・ウォーホル 50年代イラストブック』 新潮社,2000年

The Cover of the Book (American Edition)
アンディ・ウォーホル。カラフルにプリントされたマリリン・モンローやエルビス・プレスリーのイメージは、あまりにも有名だ。彼がニューヨークのアートシーンを代表するポップ・アーティストとして活躍し始めるのが1960年代。ウォーホルは、生身の人間の感触から切り離され大量生産されるイメージを、表現の場、また表現そのものとした。そんな彼の作品に代表されるポップ・アートは、独特の軽快さと明るさが印象深い。コマーシャル社会に溢れる、絶えず変化し続ける(dynamicな)エネルギーと、一方でそのめまぐるしいエネルギーの流れを透かして中心を見ようとしたときに、確かな拠りどころとなる核・根っこが見えないような空虚感。ウォーホルは“マリリン”のような作品で、繰り返すイメージと明るく強い色と色のコントラストが生み出す軽快なリズムによって、そのような現代都市の感覚を印象的に写しとった。
今回見つけた本は、そのポップ・アート以前、ウォーホルが商業イラストレーターとして活躍していた頃のイラストレーションを集めたものである。黄色やピンク、緑、青などで猫を描いたものは前にも見たことがあったが、ペンでのドローイングやそれに水彩で色をつけたものをこんなふうにまとめて見たのは初めてだった。太くなったり細くなったりしながら自由にはしるインクの線は、ユニークなあたたかみがあって見たとたんに愛着がわく。ポップ・アートの代名詞のようなウォーホルのまったく違った魅力に、びっくりしながらも夢中になった。


Male, 1955-7 (left); Sam in Pink, 1954 (right).
紙の上を滑らかにはしる線は、シンプルながら実に洗練されている。彼はジャン・コクトーが好きだったのではないかと思う。特にエロティックな雰囲気の漂うThe Boy Bookという、男の人ばかりを描いた線画は、コクトーの洗練された見事な線画を思い起こさせる。ただしウォーホルの描く線は、コクトーの本質を見抜いて線として抽出したような鋭さとは違う。コクトーの正確で明快な線は緊張感があって隙がなく、命をもってダイナミックにすべりながら、デザイン的な、それ自体で完結した世界を創り出す。ウォーホルの線もシャープで生き生きとしている。同じように際立つデザイン的センスにはドキドキさせられるけれど、彼の意識はコクトーがとことんこだわった線の力からもう少し自由である。まず何より、いかにも楽しそうだ。

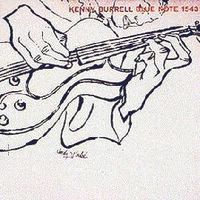
Record Covers, 1956.
ウォーホルがパーソナルなあたたかみを大切にするイラストレーターとして知られていたことも、この本を読んで初めて知った。それは絵にも十分に表れている。そうでなければあれだけ敏感なポップ・アーティストとはなりえなかった、ということでもあるのだろう。そして表現するものや方法が変わったとはいえ、洗練された軽やかさ、ユーモアといったPre-Pop時代のウォーホルの特徴は、Pop時代にも確実に受け継がれている。


"In the Bottom of my Garden" series, 1955-6.
ポップ・アート作家としてのウォーホルの作品には、「面白いな」「この感覚、なるほどな」という以上に特別な愛着をもったことはあまりなかった。ウォーホルというアーティストも、いろいろなときに気になる人ではあったが、自分の好みや興味に直接的に重なってくることはなかった。しかし、この本で50年代のウォーホルの様々なイラストレーションを見てから、イメージががらりと変わった。後の180度姿勢を転換したポップ・アートの作品すら、見え方が随分変わってきた。作品そのものに見えているものが変わったということではなく、これらのイラストレーションと無関係ではないものとして、そこにたどり着く道筋、変化の意味に興味が持てるようになったということだ。
以前は「へー」と意外に思って見ていたストーンズのミック・ジャガーのポートレートも、50年代のウォーホルを知ったことで腑に落ちるようになった。(↓)

Mick Jagger, 1975.
ウォーホルによって手が加えられたこのポートレートは、黒や灰色のカラー・マスやぐにゃぐにゃした線が入ることで、(若かりし日の)ミックのセクシーな小悪魔的雰囲気が強まっているように感じる。本人のコントロールをすっかり離れて広がるマリリンやエルビスのイメージとは違って、パブリック・イメージと生身のミックが、共にお互いが最も望むところで出会ったような、そんな印象があった。そういう意味で、ポップ・アートとしてウォーホルの作品に表現されたイメージの無機的冷たさからは逸脱しているように感じていたのだ。しかし今は、これもまぎれもなくウォーホルなんだ、と納得がいく。
本の帯には「ウォーホルになる前のウォーホル」と大きく書かれていた。しかし、むしろポップ・アーティスト“ウォーホル”になるべくして彼が捨てたイラストレーターとしての仕事の中にこそ、アンディ・ウォーホルその人が見えるような気がするのである。


<< Home