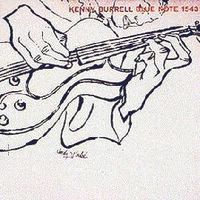Coffee and Cigarettes (コーヒー&シガレッツ)
ジム・ジャームッシュ監督,2003年,アメリカ
シネセゾン渋谷にて。

Poster of "Coffee & Cigarettes"
音楽と同じで、映画にもリズムが自分の脳波にぴったりくる、という「体感」タイプのものがある。いろいろ頭で考え始める前に、まず体が共鳴して「この映画好きだ」と反応する。そう感じさせるのは、その映画のテンポであったり、音楽であったり、色の具合であったり、キャラクターの演出の仕方であったりと様々だが、大抵において総合的な感覚なので、説明しようとするのはなかなか難しい。私にとってジム・ジャームッシュの映画は、まさにそういうタイプだ。"Stranger than Paradise" も "Down by Law" も、映画と自分の呼吸がぴったり合うような気持ちのよさがあった。今回の"Coffee & Cigarettes" もまた然りである。


"Coffee & Cigarettes" は、Coffee break中の11組のエピソード11話から成っている。"Night on Earth(ナイト・オン・ザ・プラネット)" とのときと同じ、オムニバス的な手法だ。ジャームッシュの音楽的感覚が最大限に活きるのは、それぞれ独立した様々な短いエピソードをひとつのテーマの中で組み合わせて作る、このオムニバスという形式かもしれない。ひとつひとつのエピソードの区切りは休符となって軽快なリズムを創り出すし、ひとつのストーリーにこだわらずに様々な要素を取り込んで変化をつけることができる。また、違うエピソードでも微妙に重なってくるセリフや、全場面通して使われている白黒のチェックというモチーフの繰り返しによっても、メロディーパターンのようなものを作って全体を上手につないでいる。
独特のリズム感で、それぞれ変わり者の登場人物たちがノートとなって鳴らす珍妙な音楽は、脳波に不思議な共鳴をしながら脈に乗って体の隅々まで行き渡り、なんともいえぬ嬉しさで満たしてくれる。ジャームッシュの音楽好きは、サウンドトラックとして使われる音楽だけでなく映像作りそのものに反映されて、ジャームッシュ映画を特徴付ける決定的な要素になっていると言えるだろう。


白黒がシャープできれいだ。テーブルやランプシェイドなどに必ず使われている白黒のチェックも、モノトーンの画の中できれいに映えていた。ジャームッシュはこういう画のセンスもとてもよい。それに、なんでもない不特定の時間を描くとき、時間の感覚をあまり感じさせない白黒はとても合っている。
それにしても、それぞれの組どれも居心地が悪そうに空気をもてあましていて、微妙な共感を覚えると共におかしくなってしまう。特に何をするわけでもなく、とりたてて楽しくもなければ別になんということもない時間。何かを求めて不精な手をちょっと伸ばしてみれば、そこにはいつもコーヒーがあって、タバコがある。そのちっちゃな安堵感があたたかい。
"Coffee and cigarettes, man. That's the combination."
何かと扱いにくいトム・ウェイツに調子を合わせて、イギー・ポップがウィンクまでしそうな人の良さで言う。・・・絶対ウソである。「このコーヒー、クソまずい」とこぼす双子と武器庫のじいさん、「Smoker's coughだよ」と言いながらゲホゲホ咳き込むビル・マーレイ。みんな最高だと思いながらカフェイン&ニコチンしているわけじゃない。でも、どこか居心地の悪い日常の中の、ひとつのため息からもうひとつのため息までの何ていうことはないひとときを、コーヒーとシガレットが何気なくつなぎとめてくれる。たとえまずいコーヒーでも、極上のシャンパンで夢みたいな思い出を華やかに祝うより、自分の毎日に染み込んだ、ずっとリアルな味がする。人生を祝うならコーヒーカップを鳴らそう。Cheers!

オリジナルサイト: http://coffeeandcigarettesmovie.com/
日本版サイト: http://www.coffee-c.com/